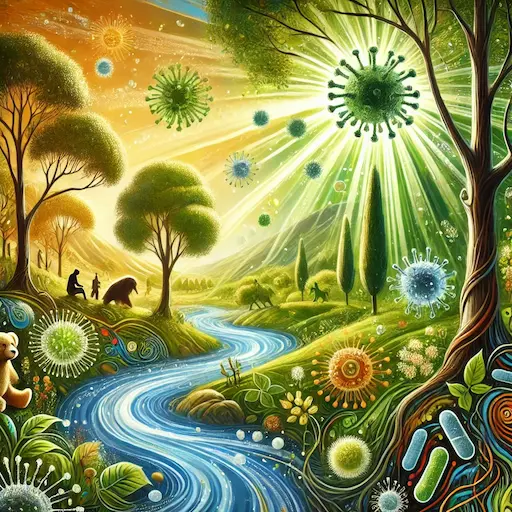
近年、新型コロナウイルスをはじめとした感染症が大きな話題となり、私たちの生活や価値観は大きく変わってしまいました。テレビ、新聞、SNSでは「感染症は恐ろしいもの」「できるだけ遠ざけたい対象」といった印象を強く打ち出しています。実際、重症化する事例や経済的被害を目の当たりにすると、どうしても“脅威”としてのイメージが先行してしまいます。
一方で、自然界の歴史を学んでみると、ウイルスや細菌は動植物を含むあらゆる生物と共存してきたことを発見できます。つまり感染症は、私たち人間の生活に突如として侵入してきた「敵」ではなく、もともと自然のサイクルの中に存在していたものと考えるのが自然です。
ここで言う「自然のサイクル」とは、ウイルス、細菌が宿主(人や動物)の中で増えたり、宿主が免疫を獲得したりしながら、環境全体がバランスをとり合う仕組みのことです。仕組み全体を「自然、世界全体」と考えてみると、病原体=ウイルスや細菌もその生態系の一部であり、“当たり前の存在”ともいえます。
このあとの記事では、「感染症も自然の一部である」という視点から、感染症と私たち人間社会がどのように関わってきたのか、その歴史や背景、そして今後のあり方について考えていきたいと思います。
具体的には、過去の大流行が社会や文化にもたらした影響、地球環境の変化と新興感染症の関係、さらには自然との共生や健康観の変化といった多角的なテーマを取り上げます。
まずはこの第1回を通して、「感染症=脅威」というイメージを少しゆるめ、自然界における病原体の役割を考えるきっかけになれば幸いです。次回以降は、病原体と人間の「長い付き合い」を振り返りながら、私たちが感染症とどう向き合っていくかを一緒に探っていければと思っています。
最新情報をお届けします
Twitter でこのサイトをフォローしよう!
Follow @tokuda_kanpou