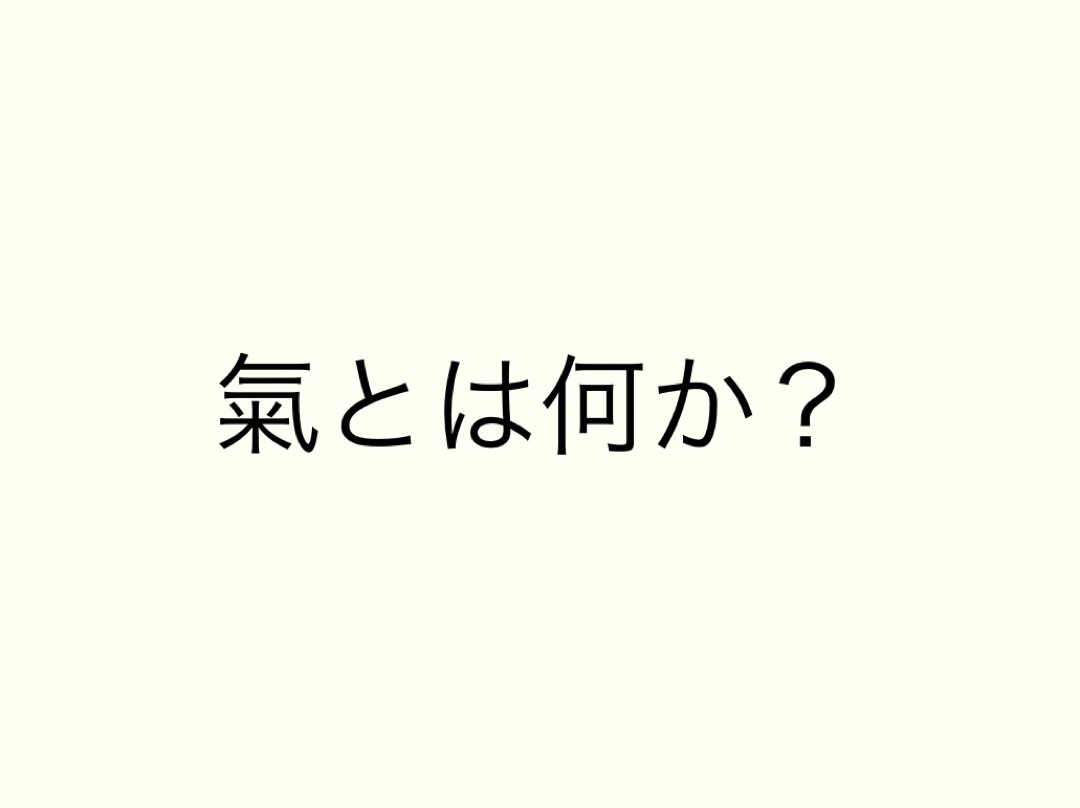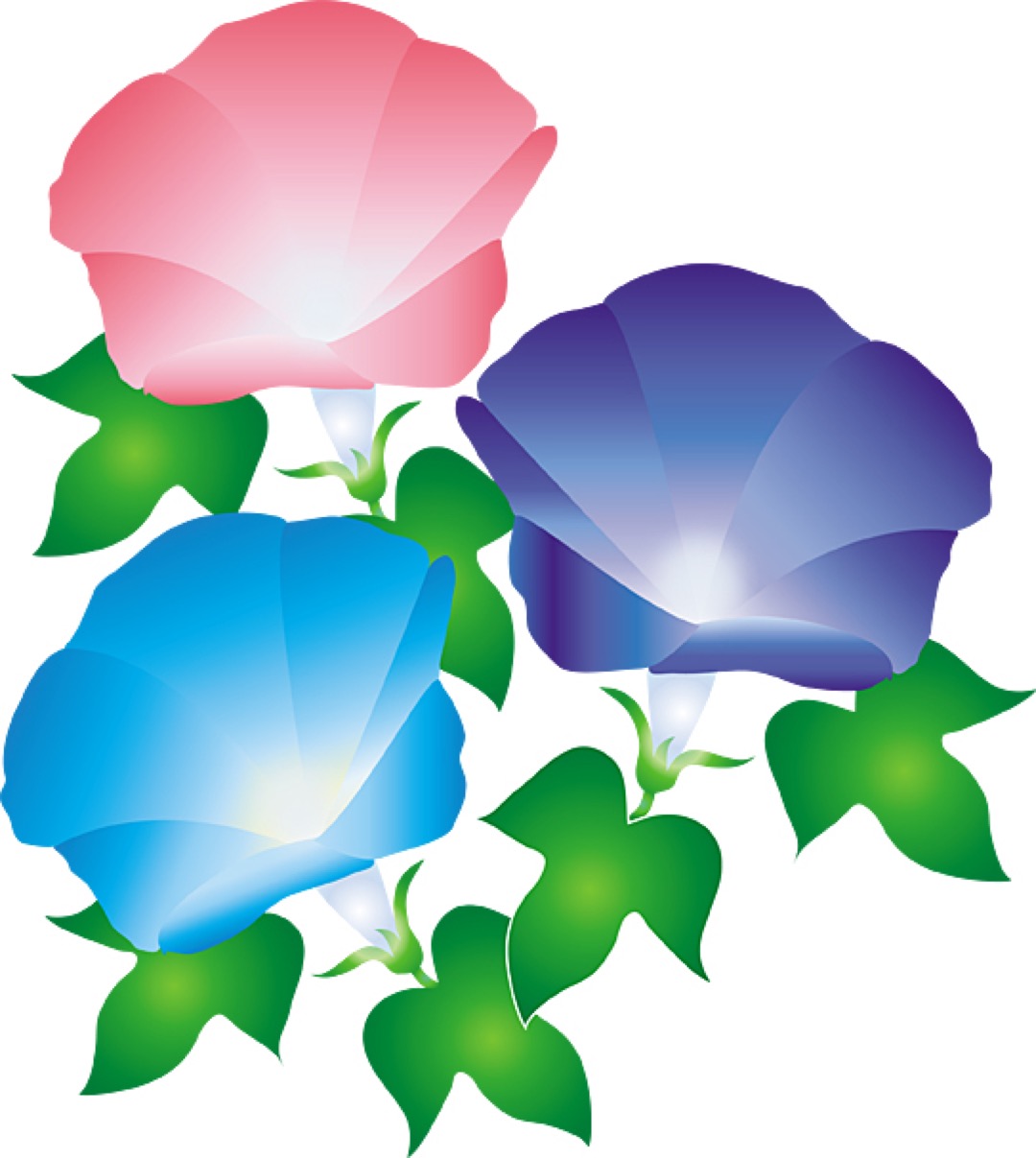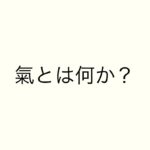その1はこちら
その2はこちら
前回まで(その1・その2)で、氣(気)を生命活動の動力源として捉える東洋医学の考え方を確認しました。本稿では、氣と五行の関係を中心に解説します。
1. 氣を人間に導入するときの2つの考え方
東洋医学で人間の身体を氣の観点から分析する際、次の2つの代表的な考え方があります。
- 氣血水(きけつすい)
- 形のあるものを「血」と「水」に分類し、形のない動力源を「氣」とみなす
- 氣と五臓
- 人体の各臓器に関連づけて、氣の働きを理解する
解説:氣血水で考えると
- 血・水:物質的な形のあるものを指し、血液や体液、リンパ液などが含まれます。
- 氣:目に見えないものの代表例であり、身体を動かすエネルギー(動力源)として位置づけられます。
2. 氣と五行学説の関連
五行学説では、万物を「木・火・土・金・水」の五つの要素に分け、それぞれが相互に生成・克制しあうと考えます。ここで注目したいのは、人間における「氣」の働きをどの要素に結びつけるか、という点です。
ポイント:氣の観点をさらに「人間の氣」に限定すると、氣は“呼吸”と深く結びつきます。
五行にあてはめると、呼吸をつかさどる「肺」が金(肺=金)に対応し、氣と直接的に関わる臓器として位置づけられます。これを踏まえると、
- 氣に五行学説を入れる → 「呼吸」と「肺臓」が中心的役割を担う
という図式が成り立つのです。
3. 古典の裏づけ:素問「五臓生成論」
なぜ肺と氣がこれほど深く関係するのでしょうか。それは、『素問(そもん)』という東洋医学の古典に明確な記述があるからです。
諸気者 皆属於肺
(しょきしゃ みな これ はいぞうに ぞくす)
意味:人体のあらゆる「氣」は、すべて肺に属する
この一文が示すように、肺がしっかり呼吸を行っていれば、氣の巡りも良好であると考えられます。逆に肺の働きが低下すると、氣のめぐりが滞り、全身に影響が及ぶ可能性が高まるのです。
4. 「心臓ではなく呼吸が止まると死ぬ」の考え方
東洋医学において、「氣」という視点を中心に見ると、人は“心臓が止まって死ぬ”というよりも、“呼吸が止まって死ぬ”と捉えられます。これはあくまで「氣=呼吸」という論点からの見方であり、氣を司る肺の機能が途絶えることが、すなわち生命活動の終わりと考えるわけです。
5. まとめ
- 人間の身体における氣の捉え方
- 「氣血水」:血や水などの有形物との対比で捉える
- 「氣と五臓」:肺との関連を重視する
- 五行学説との結び付き
- 呼吸を司る肺は五行の「金」に属し、全ての氣が肺に集まると古典で説かれている
- 氣が止まる=呼吸が止まる
- 東洋医学の氣の概念を中心に見ると、“心臓が止まる”のではなく“呼吸が止まる”ことが死につながると考えられる
6. 次回予告
本シリーズ「氣とは何か?」はここで一旦終了となります。次回は、東洋医学で重要な基礎概念のひとつである**「陰陽学説」**を扱います。氣と合わせて学習することで、より包括的に東洋医学の理論を理解できるようになるでしょう。