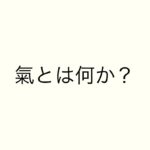経絡治療の勉強会に参加しますと
経絡の流注を知らない先生が多いことに気づきます
経絡の流注とは
その経のツボを順番に結んだ線ではありません
どの経絡を治療すれば治るのかの診断や
病になっている経絡が本当に治ったかどうかの確認は
ツボを結んだ線を調べるだけでは不十分だと思います
本当の流注はおそらく複雑怪奇で
「これが流注だぞ!」と示すことは難しいです
ですが、経絡治療を目指す鍼灸師であれば
なんとかして経絡の流れを詳しく知って
診断や治療結果をよくしたいものです
ここからは私の学習の方法をご紹介したいと思います
一番まとまっているのは、経絡治療講話
どの本を読めば良いかですが
ほとんどの本は古書も含めて
霊枢経脈編からの引用です
さらに霊枢経脈編の解説としては
類経、十四経発揮
などが分かりやすいと思います
一番最初にオススメしたいのは
一番まとまって経絡の流注が書いてあると思う
経絡治療講話です
その次は図解が素晴らしい「図解十四経発揮」
その次にオススメなのは
「図解十四経発揮」です
これはとにかく細かく図にしてあります
古典の内容に忠実な図なので
漢文の理解の助けになってくれます
最後は「古典から学ぶ経絡の流れ」
最近発売された本ですから
知らない鍼灸師の方も多いと思います
この本があるのでこの記事を書こうと思いました
内容は
霊枢経脈編の解説
↓
類経ではどういっているかの全文
↓
経別、経筋
↓
馬王堆皇書(最古の医学書)
など充実した内容を
肺経→大腸経→、、、、、→肝経までしっかりまとめてあります
図解が少ないので三番目にオススメですが
ベテランの先生は一番最初に買っても良いかと思います
徳田漢方はり院 徳田和則