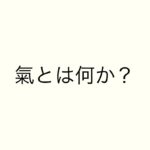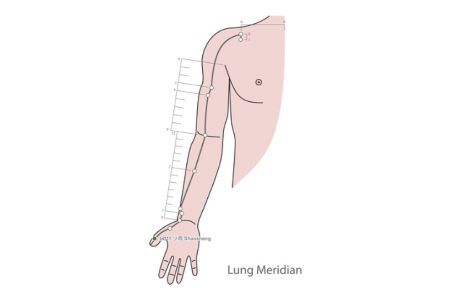
太陰肺経の流注ですが
まず、wikiにある霊枢の流注を載せます
太字になっているところについて
臨床的な解説を書いています
wikiの流注
中焦(中脘)に起こり
下って水分穴で大腸を絡い
還って胃口を循り
膈を上って肺に属する。ついで気管、喉頭を循り
横に腋下に出て上腕内側を循り
少陰・心主の前を行き肘窩(尺沢穴)に下る。前腕の前面橈側を循って橈骨動脈拍動部に入り
母指球より母指末端に終わる。その支なるものは、手関節の上(列缺穴)より示指の末端に入り
手の陽明大腸経に連なる。
以下、太文字になっているところについて
臨床的な解説を加えています
経絡全体の流注が中焦→肺経なのは氣血栄衛を作るため
肺経は中焦から始まります
これは経絡の中を流れる氣血栄衛が
中焦の飲食物+肺臓の呼吸作用
でできるので、最初に肺経が来るのです
氣血栄衛の病の時は
呼吸の気と飲食の気の調整が必要です
霊枢:栄衛生会篇
「人は氣を穀に受け、穀胃に入り、以って肺に伝わる
五臓六腑皆以って氣を受く 清なるものを栄とし濁なるものを衛とする」
水分穴は小腸と大腸の境い目
水分穴は小腸と大腸のさかい目ですので
津液の病があるか診るときには水分穴を調べます
霊枢:経脈篇、大腸に
「是れ津液を主として病を生ずる所の物は」
とあります
大腸経の所生病は津液の病であることがわかります
気管、喉頭をめぐるのは
wikiでは「気管、喉頭をめぐる」となっていますが
東洋医学の古典では咽喉と表現することが多いです
咽喉をに関係ある経絡は
肺経
胃経
脾経
心経
腎経
肝経
が重要でしょう
足の陰経は舌や頭まで流注します
心経も舌に関係あります
胃経は食道や唾液の関係でしょう
肺経はもちろん呼吸や気管に関係があります
腋下に出て、中府、雲門からは教科書通り
中府、雲門以降は教科書どおりです
あとで出てきますが
缺盆穴と中府、雲門の関係が
少し難しいかもしれません
缺盆穴については胃経のところで
詳しく書きます
大腸経に続きます
-
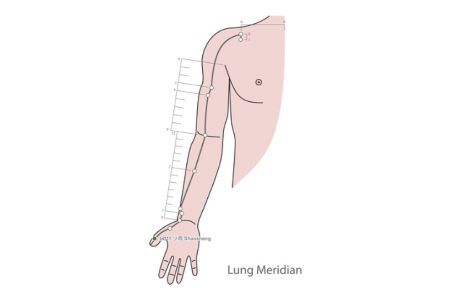
-
陽明大腸経流注の臨床的な解説
陽明大腸経の流注ですが まず、wikiにある霊枢の流注を載せます 太字になっているところについて 臨床的な解説を書いています 大腸経の流注、wikiでは 示指末端(商陽穴)に起こり 示指の橈側白肉際( ...