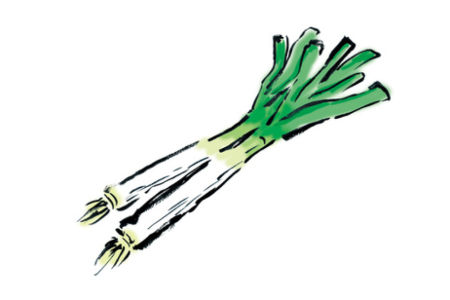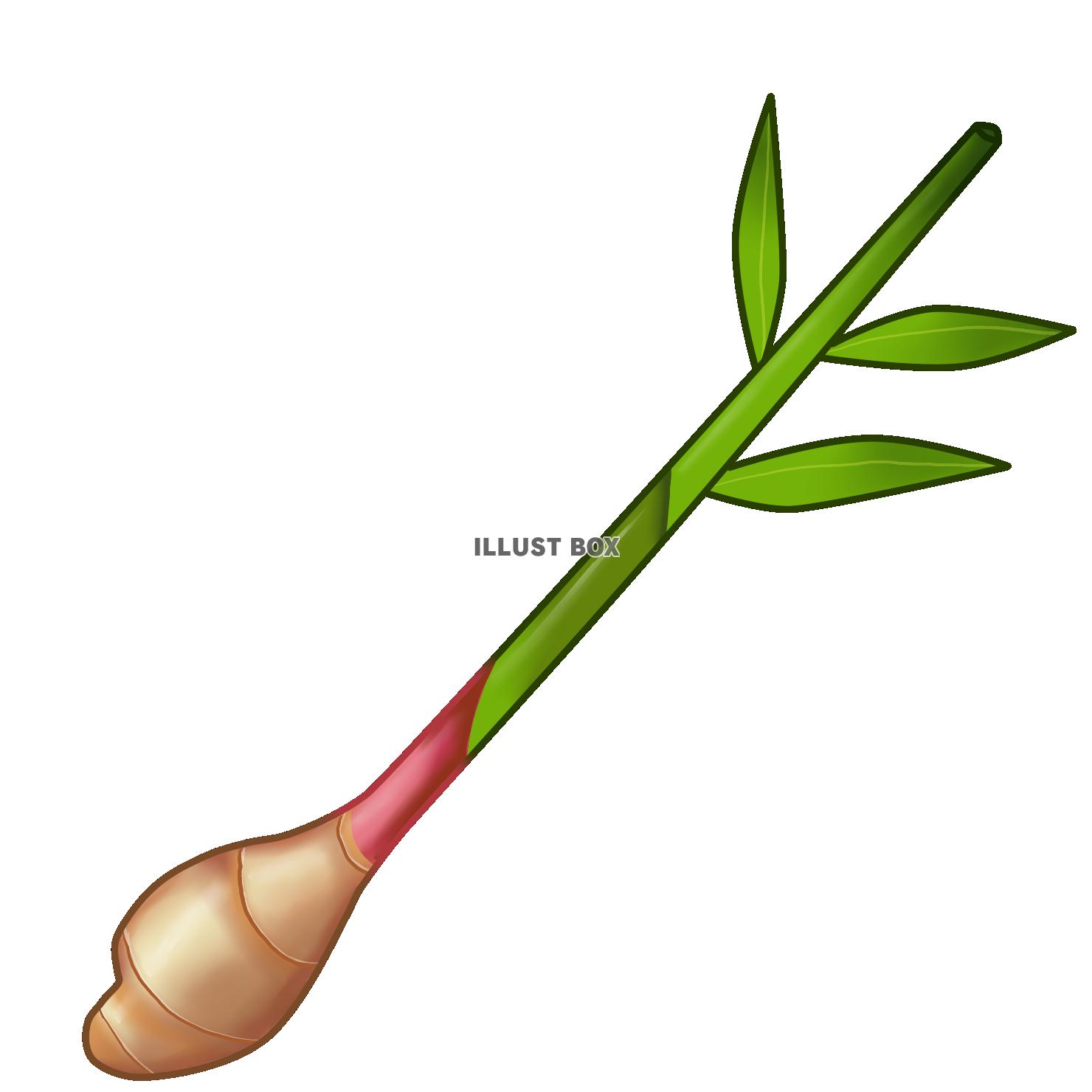東洋医学では、食材にはそれぞれ“旬”があり
野菜や果物だけでなく、実は肉類にも旬の時期があると考えます
お肉にも五行→木火土金水の性質があるのは
ほとんど知られていないと思います
東洋医学における「旬」の考え方
東洋医学では、食べ物にはそれぞれ「五行(木・火・土・金・水)」「五味(酸・苦・甘・辛・鹹)」があり
それが人体の気血水のバランスに影響を与えるとされています。
野菜や果物の旬は有名ですが、動物の肉にもその性質があります
適した季節に摂取することで、体調を整える効果が高まります。
魚には東洋医学的な旬はない
サンマやサケは秋に旬です、ブリは冬に旬で美味しいですね
ですが、東洋医学的にお魚には旬がありません
もちろん冬のブリは脂が乗っていてとてもおいしいのですが
冬→五行の水の性質は持っていません
さて本題、お肉を五行学説で分けると
木・火・土・金・水
↓
春・夏・土用・秋・冬
↓
鶏・羊・牛・馬・豚
五行ではこの様な対応になります
五行の対応について、くわしくはコチラ
それぞれのお肉の特徴について、くわしく書きます
春(木)→鳥肉
春は冬眠から覚め身体が徐々に活性化していく時期です。
東洋医学では、冬にため込んだものを春の“肝”でデトックスする時期です
解毒に関連するトラブルが起こりやすいです
例えば、花粉症などのアレルギーですね
春に鶏肉を食べると肝臓を助けて体をキレイにします
ただ、最近の鶏肉については安く売るために
コストダウンの影響で、不健康に育てられた鳥肉は不純物が多くて
かえって肝臓に負担をかけます
少し高価になりますが、地鶏などは安心で肝臓を助けると思います
夏(火)→羊肉 ラム、栄養価的に豚肉もおすすめ
ラムやジンギスカンですが東洋医学では夏が旬です
北海道で夏に食べるジンギスカンは最高です!
ジンギスカンといっしょにいただく玉ねぎも
春夏が旬の時期ですのでダブルで美味しいですね
夏の五行の味は苦味です
つまり、ジンギスカンにビールはもっと最高ですね!
また夏は高温多湿の環境下で体力消耗が激しく、消化器系の負担が増えがちです。
東洋医学的には、冷たい飲食物だけに偏らずに
適度な熱性を持つ肉をとることが大切だとされています。
その意味で羊肉は最適です
また、豚肉は東洋医学的に「精」が豊富とされています
現代的に言うと、ビタミンB群が豊富で、疲労回復を助けると言われているのに似ています
体力消耗が激しい夏場にはおすすめです
沖縄で豚肉が盛んに食されているのにも意味があると思っています
土用→牛肉
牛肉は東洋医学で胃に良いとされています
現代人は糖分過多な食生活の方が多く
糖質過多ですと胃が悪くなりやすいです
そうすると胃が肉類を受け付けません
肉があまり食べれなくなってしまった方は
牛肉から召し上がっていただくのがオススメです
秋(金)→馬肉
昔は、カゼをひいたら馬刺しを食べろ
といったそうです
秋は風邪を引きはじめる時期です
最初の風邪をしっかり治さないうちに
重ねて風邪を引くのは慢性病の大きな原因です
馬の肉をたべて秋の氣を育てれば
カゼに強くなるということでしょう
ですが、熊本以外で馬肉は手に入りにくいです
風邪を引きやすい方には「長ネギ」をおすすめしています
冬(水)→豚肉
豚肉は東洋医学的には「精」を養います
精とは体力の貯金のことです
冬はあまり動かないで
カラダの中に体力の貯金をするのがよいです
貯金がいくらあるかで
病気になりやすいかどうかが決まります
そういう意味で、豚肉は冬だけでなく
年中、季節問わず食べていくことをオススメします
ちなみに、陰陽でわけたらどうなる?
お肉を五行で分けたら以上のようになります
陰陽でわけて食べていただいてもよいので
陰陽でのわけかたも書きます
- 春夏は陽で
- 秋冬は陰です
春夏→鳥、羊、牛
秋冬→馬、豚、牛
となりますが
豚のところでも言いましたが
豚が養う精は一年中必要ですので
春夏→鳥、羊、牛、豚
秋冬→馬、豚、牛、豚
がよいと思います
ご参考になれば幸いです
野菜の旬についてはコチラ
追記、なぜお肉、お魚をオススメするのか?
治療のあとは胃腸が整い
栄養が吸収されやすい状態になります
ここで適切な食事をしていただきますと
治療の効果が倍増します
身体の構成物質であるタンパク質を摂って
カラダを新しいモノにしていくと
ご自身が本来持っている健康な体に戻れます
タンパク質の豊富な
お肉かお魚を食べると良いと思います