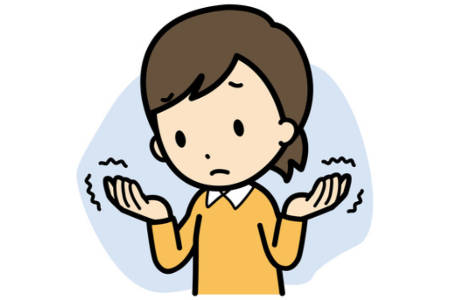
初めてしびれを感じると、「神経が傷んでしまったのでは」と不安になりがちです。
しかし実際には、神経そのものよりも「血行不良」や「栄養不足」、「運動不足」など、生活習慣に根ざした要因でしびれが出るケースがとても多くみられます。
ここでは、東洋医学の専門家として、しびれの主な原因・改善策・部位別の注意点などを詳しく解説します。初心者の方にも分かりやすいように専門用語には簡単な説明を加えています、ぜひ参考にしてください。
1. なぜしびれが起こるのか
● 血行不良が大きな原因
しびれの多くは慢性的な血行不良が関係しています。ストレスや食事の偏り、運動不足などによって血液が十分に巡らなくなり、末端神経への栄養が届きにくくなるのです。神経が直接傷んでいるわけではないため、改善できる余地は十分にあります。
● 東洋医学で見る「しびれ」の考え方
東洋医学では、しびれを「重痛(じゅうつう)」とよび、「金(きん)」という五行の要素の乱れと関連づけます。金は肺に通じ、肺が深い呼吸をつかさどるため、呼吸が浅い生活が長く続くと血液循環や気(エネルギー)の流れが滞り、しびれが起こりやすくなると考えられています。
- 五行(ごぎょう):木・火・土・金・水という自然界の要素に人間の身体をあてはめて総合的に捉える東洋医学の概念。
2. しびれはなぜ治りにくいのか
しびれは、多くの場合「生活習慣に原因がある」ため、根本的な対策をしない限り症状が改善しにくいとことが多いのです。たとえば、
- ストレスにより体が常に緊張し、血流を悪くしている
- タンパク質不足やビタミン・ミネラル不足などによって神経が過敏になりやすい
- 運動不足で筋肉が衰え、血行が悪くなっている
これらが同時に起きている場合、原因をひとつずつ見直していかないと慢性的なしびれが続いてしまうことが多いのです。
3. 主な原因別の詳しい対策
(1)ストレスによる血行不良
ストレスをゼロにするのは難しいものです。ですが、うまく発散したり、ほかの要因を減らしたりして血流の滞りを解消することが重要になります。特に東洋医学では、ストレスで全身のバランス(陰陽五行)が乱れることで体の各部に不調が出ると考えます。
- ストレス対策の例
- 軽いウォーキングや散歩を習慣にする
- 深呼吸や軽いストレッチで緊張をほぐす
- 趣味やリラックスできる時間を意識的につくる
- 同じストレスで同じ臓器に負担がかかっている時には五臓を調節する鍼灸治療は有効です
(2)栄養不足による血行不良(タンパク質不足)
「神経が過敏になる」「血液の質が落ちる」といった問題が、しびれには大きく影響します。特にタンパク質は血液の材料にもなるため、食生活でしびれ対策をしたい場合、次の点に注意すると効果的です。
- タンパク質を意識的に増やす
- 肉・魚・卵・大豆製品をしっかり取り、筋肉や血液の材料を補給
- 炭水化物を少し控えめにし、その分たんぱく質中心の食事を心がける
- 野菜や海藻などでビタミン・ミネラルを補う
- 炭水化物を抑える理由
- 炭水化物過多になると糖質の摂り過ぎで血行が乱れ、血液ドロドロの原因にもなる
- 炭水化物を減らして良質なたんぱく質を増やすことで、全身の血液循環がスムーズになりしびれの改善につながる
(3)運動不足による血行不良
運動不足が続くと、筋肉が衰えて血液を押し流すポンプ機能が低下し、手足の末端まで血液が届きにくくなります。その結果、しびれや冷えが出やすくなるのです。
- 運動不足対策の例
- 外を歩く時間を毎日10分でもいいので少しずつ増やしていく
- しびれが強い場合は、まず鍼灸治療などで体力を回復させてからウォーキングを始める
- 軽いストレッチや体操も、血行促進には有効
4. 部位別に見るしびれの注意点
● 小指と薬指のしびれ
東洋医学では、小指と薬指は心臓や心包系に関係が深いとされます。小指や薬指がしびれ、胸の痛みや動悸などを伴う場合には重大な病気が隠れていることもあり得るため、できるだけ早めに医療機関を受診するのがおすすめです。
● 親指のしびれ
親指のしびれに加えて、めまい・不眠・頭痛などの症状がある場合は、早めに検査を受けておきましょう。東洋医学では頭部や首の緊張、気血の滞りとの関連を疑うことがあります。
● かかとのしびれ
かかとのしびれは、先天の精(せんてんのせい)不足とされます。
- 「先天の精」とは、体力や免疫力の“貯金”のようなもの
- 普段の栄養(後天の精)が不足すると、貯金を切り崩すように体力を消耗してしまう
- 皮膚がカサカサしたり髪の毛にツヤがなくなったりし始めたら要注意
食事の改善や鍼灸治療で胃腸の調子を整え、体力・栄養面を補強することが大切です。
● 手足全体のしびれ
手も足も広い範囲でしびれる場合、糖尿病など全身性の疾患を疑うことがあります。東洋医学的には、脾臓(ひぞう)の働きが低下しているという見方をすることが多いです。炭水化物の過多や「精神的な消化不良」(悩み事の抱え込みすぎなど)が原因で脾臓が弱り、全身のめぐりが悪くなっているかもしれません。
● 腰から足にかけてのしびれ
いわゆる坐骨神経痛やヘルニアが疑われることが多い部位です。一方、東洋医学では「肝(かん)・胆(たん)」の不調が血行不良や老廃物の滞りとして現れていると考えます。体の解毒が追いついていないことが多いです。インスタント食品やファーストフードなど添加物を多く含む食品を控え、肝臓に負担をかけない生活を心がけましょう。
5. 東洋医学による鍼灸治療のアプローチ
● 全身の血行促進と自律神経の調整
鍼灸治療では、ツボを刺激することで血流の促進や自律神経のバランス調整を行います。特に東洋医学の考え方では、単に局所だけでなく、内臓機能・精神面・生活習慣まで含めて総合的にアプローチするのが特徴です。
● 胃腸機能・呼吸の回復
血行不良でのしびれのときは、胃腸の消化力低下や呼吸が浅い状態とも深くかかわっています。鍼灸で胃腸を整え、呼吸を深めるツボを選ぶことで、基礎代謝が高まり、回復力が引き出されます。
● 自然治癒力を高める
鍼灸によって血行を改善し、体が本来もつ自然治癒力を最大限に発揮させることで、しびれの根本原因を取り除くアプローチが期待できます。鍼やお灸は痛みが少なく、リラックス効果も高いので、ストレスが原因の方には特におすすめです。
6. まとめとアドバイス
- しびれの大半は血行不良や生活習慣に起因
- ストレス軽減、タンパク質中心の食事、適度な運動がしびれ改善の大きなカギ
- 東洋医学では五行説による内臓の働きの偏りや呼吸の浅さを重視し、全身を整える
- しびれがひどい場合や特定の指・部位のしびれが続く場合は西洋医学的な検査も受けておくと安心
初心者の方でも、しびれの原因にはいくつかの要素があることを理解いただけたかと思います。もし「長期間続いている」「軽減しない」といったお悩みがあれば、遠慮なく専門家に相談してください。鍼灸治療は薬を使わず、体質やライフスタイルを含めてサポートできる方法です。生活習慣の改善とあわせることで、しびれが根本から解消し、健康な身体へと近づくお手伝いができるでしょう。
この記事を書いた人
- 院長:徳田 和則
- 鍼灸師・柔道整復師
- 2008年 徳田漢方はり院を開業
- 北海道漢方鍼汪会 会長
- 「自然で健康な身体にもどるためのお手伝い」をモットーに、丁寧なカウンセリングと東洋医学ならではの全身治療を行っています。
「しびれは治りにくいもの」とあきらめず、ぜひご自身の生活習慣を見直しながら、必要に応じて専門家にご相談ください。東洋医学と鍼灸の力で、しびれのない健やかな日常を取り戻しましょう。
