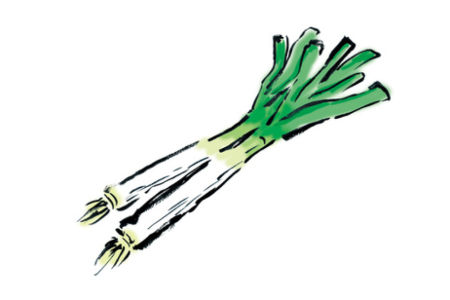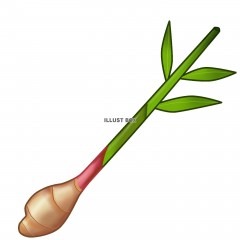
しょうがの旬や性質などを東洋医学で分析しますと、世間で言われている体を温めるという性質は少し違うのでは?ということも言えそうです
以下、詳しく書きます
野菜の旬は春夏と秋冬でわけます
春夏の野菜の特徴ですが
空中にあるもの、くきの部分、生で食べられる
などがあります
キャベツ、たまねぎ、きゅうり、トマト、なす、ピーマンなどです
体をサッパリさせてくれます、余計な熱を取る、といったイメージでしょう。
とても暑い時にトマトを食べると体がサッパリします
お盆の時にご先祖様があの世から帰ってくる際の乗り物として用意するもので、キュウリとナスに割り箸や爪楊枝などで足を付けて、馬や牛の形にするのは、暑気をキュウリやナスが取ってくれるからでもあります
秋冬の野菜の特徴ですが
根っこに近い、根っことして機能している、煮たり焼いたりで食べるもの
長ねぎ、ほうれん草、白菜、大根、レンコンなどです
こちらは春夏と逆で体を温めてくれます
大体がお鍋に入っている具材ですね
体が温まると思います
しょうがは初夏に収穫する
さて生姜の話に戻りますがしょうがは初夏に収穫します
カラダをサッパリさせます
余計な熱を取ります
しょうがはカラダを温めるの?
皆様が一つ間違えやすい事があります
それは、冷え性の人が
身体を温める目的で生姜を食べてしまう事です
しょうががカラダを温めるように感じるのは
辛味があるからだと思います
辛味は発散作用があります
辛いものを食べると汗をかきますね
汗をかくからカラダが温まるように感じます
しかし、汗をかくと皮膚表面から熱が発散されます
体の中から余計な熱が取れてサッパリします
夏に汗が出にくいと体の中がモヤモヤしますね
カゼの引き始めに効くと言われていますが?
東洋医学でいうカゼとは
悪寒(さむけ)、発熱、頭痛、関節痛などがあるものです
外からの邪気(ウイルス)とカラダの正気が戦っている状態です
その場合解熱しなければなりません
カラダをサッパリさせるしょうがは
風邪の引き始めに効果があるとおもわれます
薬味は食べる薬
薬味と呼ばれる野菜には薬効成分がたくさん含まれています
ネギ、しょうが、大根おろし等です
ネギ、大根については別にページを設けましたので
ご参考ください