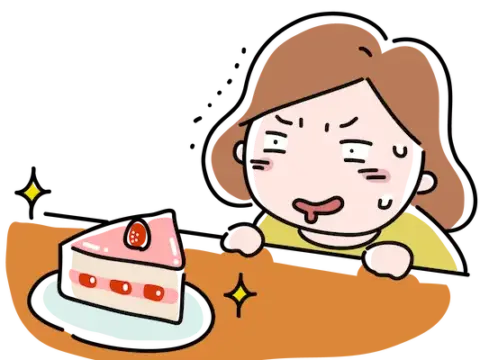
甘いものはカラダに悪いから、、、と言いつつ、ついつい食べ過ぎてしまうのが
甘いもののあま~いワナですかね(^_^)
「カラダに良くないとわかっているのに、甘いものがやめられない」
「疲れたときやストレスが溜まると、つい手が伸びてしまう」
――こうしたお悩みをお持ちの方は多いと思います。
実際、甘いものは気分転換やリラックスに役立ちますし、完全に我慢するのは難しいですよね。しかし東洋医学の視点で見ると、甘いものの過剰摂取は体内に”湿(しつ)”という余分な水分や老廃物を生み出し、関節痛や慢性疲労など様々な不調につながる可能性があるのです。
本記事では、東洋医学の基本理論「陰陽五行(いんようごぎょう)」を用いて、甘いものを食べ過ぎるとどのように体へ影響するのか、そのメカニズムをわかりやすく解説します。「じゃあ、まったく甘いものを食べられないの?」と不安になる方に向けて、上手な付き合い方も同時にご紹介していきます。
1. 東洋医学における「甘い味」の位置づけ
陰陽五行とは?
東洋医学では、万物を「陰と陽」に分け、さらに自然界のあらゆる事象を「木・火・土・金・水」の五つの要素(五行)に分類します。
この理論によって、人間の身体や感情のバランス、さらには食物の味までも体系的にとらえようとするのが「陰陽五行説」です。五行は互いに「生み出す関係(相生)」と「抑制し合う関係(相剋)」があるとされ、バランスが崩れると、身体や心に不調が出やすくなると考えられています。
五行の分類
- 木(もく):酸味、風
- 火(か):苦味、熱
- 土(ど):甘味、湿
- 金(ごん):辛味、燥
- 水(すい):塩味、寒
甘味=「土」に属する
甘いものは五行のうち「土」に分類されます。
土は植物が育つための養分がある大地をイメージしていただくとわかりやすいと思います。適度な甘味は「栄養」として体を滋養し、疲労回復やリラックスをもたらす重要な要素です。
しかし、甘いものを過剰摂取すると”土”が過剰に働いてしまい、体内で邪気(じゃき)となって”湿”を生むと考えられています。この「湿」は、むくみや体の重だるさ、痛みなどを引き起こす原因になってしまうのです。
2. 「湿(しつ)」が体にもたらす悪影響
湿が溜まりやすい日本の気候
日本は高温多湿の気候が特徴的で、もともと空気中に水分が多い環境にあります。
そのため、外部から取り込まれる湿気は体に溜まりやすく、体内の余分な水分をうまく排出できない方ほど不調が出やすくなると思います。特に以下のような状態の方は注意が必要です。
水分調節が苦手なサイン
- トイレに行く回数や尿量が少ない、あるいは多すぎる
トイレの回数が極端に少なかったり、逆に頻尿だったりする場合、体の水分代謝がうまくいっていない可能性があります。体内に湿が溜まりやすい状態といえます。 - 汗をかきにくい、あるいは必要以上に汗が出る
暑い日でもほとんど汗をかかない方や、逆に少し動いただけで大量に汗が出る方は、体の水分バランスが乱れているかもしれません。こうした方は、特に甘いものを過剰に摂ることで”湿”をため込みやすく、慢性的なだるさやむくみ、関節痛のリスクが高まります。
関節痛や慢性疲労につながる
東洋医学では、体の中に生じた”湿”は関節に溜まりやすいとされています。
湿気の多い日は関節が痛むという方がいるように、過剰な湿が体に滞ると、以下のような症状が起こりがちです。
湿が引き起こす主な症状
- 関節の痛み・腫れ
湿気が溜まることで関節に炎症を起こしやすくなります。特に膝や肘、指などの関節が重だるく感じたり、天気の悪い日に痛みが増したりする場合は、湿が原因かもしれません。 - 慢性疲労・だるさ
体全体に重苦しさが出て、疲労が抜けにくくなります。朝起きても体が重い、午後になると急激に疲れるといった症状がある方は、体内に湿が溜まっている可能性があります。
「なんとなく体が重い」「疲れやすい」という方は、甘いスイーツや清涼飲料水などを頻繁に摂っていないか、食習慣を見直すことが大切だと思います。
3. 甘いものが脳の活動レベルを上げる?実は下げます
一般に言われる「脳には糖分」は本当?
「脳のエネルギー源はブドウ糖だから、甘いものは脳にいい」とよく言われますね。
しかし東洋医学的な見方では、甘味=土が過剰になると脳(=水)を抑え込む「土剋水」という現象が起こるとされます。
「水」は脳と関係しますので、つまり、甘味をとりすぎると脳の働きを低下させる可能性があるというわけです。
休憩時間にちょっとした甘いものを食べると、「ホッとした」ような感覚になりますよね。実はこれ、脳が休息モード(活動レベルが下がる)になっていると考えられます。
ワンポイント実験
休憩中に砂糖入りのコーヒーと、砂糖なしのコーヒーの両方を試してみてください。
休憩後の仕事や勉強の集中度を比べると、砂糖なしの方が頭がスッキリしている…と感じる方は多いと思います。甘いものを摂ると一時的にリラックスできますが、その後の集中力には影響が出やすいのです。
4. 甘いものと上手に付き合うためのポイント
間食より「食後」に食べる
甘いものを完全に絶つのは難しいでしょうし、ストレスの原因にもなりかねません。
東洋医学でも「適度な甘味は滋養になる」と考えます。大切なのは、できるだけ「食後」にまとめて摂取することです。
食後がおすすめの理由
- ビタミン・ミネラル、消化酵素が動いている
食事と同時に血糖コントロールや消化が進むので、甘味の処理を一気に行いやすくなります。食後のデザートとして楽しむことで、体への負担を減らすことが期待できます。 - 間食を減らし、内臓を休める時間をつくる
食事の合間に余計な糖分を取らないようにすると、内臓が回復する余裕が生まれます。胃腸が休める時間を確保することで、消化機能が整い、湿が溜まりにくくなると思います。
水分調節が苦手な人は要注意
先述のとおり、トイレや汗の調子が乱れている方は、とくに甘味の摂りすぎに気を配る必要があります。
体内に入りすぎた湿を排出できず、慢性的な浮腫みや疲労の原因になってしまうからです。以下のような習慣を意識し、体内の”水はけ”を良くすることも重要な対策となります。
水分代謝を整える習慣
- 水分を適度にとる
一度にたくさん飲むのではなく、こまめに少しずつ水分補給をすることで、体の水分バランスが整いやすくなります。 - 塩分のとりすぎにも気をつける
塩分を摂りすぎると、体が水分を溜め込もうとして、むくみや湿の原因になります。甘いものと同様に、塩分も適度な量を心がけましょう。 - お風呂や軽い運動で発汗を促す
湯船にゆっくり浸かったり、ウォーキングなどの軽い運動で汗をかくことで、体内の余分な湿を排出しやすくなります。無理のない範囲で、日常生活に取り入れてみてください。
5. まとめ:甘味は適度が大事。うまく付き合う方法を身につけよう
甘いものは東洋医学で「土」の要素に当たり、適量であれば身体を滋養し、疲れを癒やす力となります。
しかし食べ過ぎれば湿気となって溜まり、関節痛や慢性疲労、脳の活動低下などにつながる恐れがあります。「毎日頻繁に甘いものを食べている」「むくみやだるさが気になる」という方は、まずは以下のポイントを見直してみてください。
今日から実践できること
- 甘味の摂取タイミングを「食後」に
間食を減らし、デザートとして食後にまとめて摂ることで、内臓への負担を軽減できます。 - 水分バランスのとり方を工夫する
こまめな水分補給、適度な塩分調整、お風呂や軽い運動で発汗を促すことで、体内の湿を排出しやすくなります。 - 休息時間を確保する
食事の合間は内臓をしっかり休める時間に当てることで、消化機能が回復し、湿が溜まりにくい体質に近づけると思います。
東洋医学的な考え方を取り入れることで、甘味との上手な付き合い方が見えてくるはずです。
食後のデザートをゆっくり味わい、その分、食事の合間は内臓をしっかり休める時間に当てましょう。そうすれば、甘いものをまったくやめなくても、体の調子を整えつつスイーツも楽しめるようになると思います。
執筆者
徳田 和則(とくだ かずのり)
東洋医学と鍼灸の臨床経験を重ね、2008年に「徳田漢方はり院」を開業。鍼灸師・柔道整復師として多くの患者様の治療と健康指導に携わり、北海道漢方鍼汪会 会長を務める。湿度の高い日本特有の気候や生活習慣を踏まえ、無理なく取り入れられる東洋医学の知恵を伝えることをライフワークとしている。
上記の内容を参考に、ぜひ日々の甘味との付き合い方を振り返ってみてください。体質や生活リズムに合わせて少しずつ工夫を重ねることで、甘いものによる不調を防ぎ、健やかな毎日を送れるようになると思います。
