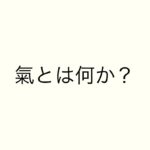北海道漢方鍼汪会活動内容
はじめに
北海道漢方鍼汪会の経絡治療勉強会は、昭和の伝統を受け継ぎながらも、現代の臨床現場で即戦力となる技術を体系的に学ぶための場です。
目的は、単なる理論習得に留まらず、古典医学の奥深い知識と、実際の施術現場で活かせる実践技術の両面から、鍼灸師としての真の臨床力を養うことにあります。
この勉強会では、故二階堂宜教先生がまとめ上げた初心者用テキスト「本治法」を中心に、2~3年かけて段階的に学習を進めます。ここでは、各章ごとの学びの意義や実践方法を、従来の枠を超えて徹底的に掘り下げています。
カリキュラムの全体像

非売品専用テキスト「本治法」に基づくカリキュラムは、古典医学の基礎理論から臨床応用に至るまで、10章で構成されています。
各章は、後の臨床実践に直結する重要な知識と技術が体系的に整理されています。
第1章:基礎理論
-
古医書医学の考察とその特徴
- 初学書としての意義
古代の医書に記された知識は、現代の鍼灸治療の根幹をなすものであり、自然界と人体の相互関係や生命現象の基本原理を理解するための出発点です。 - 自然と身体の調和
自然界の法則がどのように人体の構造や機能に反映されているのか、そしてそれが如何に治療に応用されるかを多角的に学びます。 - 氣論の徹底理解
氣は生命エネルギーの源であり、あらゆる動態の原動力です。氣の概念を正確に捉えることが古典医学を取得する鍵になります。
- 初学書としての意義
-
陰陽論・五行論
- 陰陽の原理は、万物のバランスと変化の基盤です。具体例を豊富に挙げ、実際の症例における陰陽の適用方法を徹底的に解説します。
- 五行論では、五行の相生相剋とその医学的応用、さらに「制化の関係」(三者の関係)を詳細に学ぶことで、病態の解析や治療法の選定に役立つ実践的な視点を習得します。
第2章:臓腑論
- 五臓六腑と奇恒の腑の理解
臓腑論は、身体の内部構造と機能を捉えるための枠組みです。各臓腑がどのように連携し、病態を引き起こすかを詳細に分析。
第3章:経絡論
- 十二経絡の全体像と詳細解析
経絡は人体の循環のネットワークであり、その正確な理解が診断と治療の鍵となります。- 各経絡の走行、特性、関連する臓腑との関係、そして経節・経別・十五絡といった細部まで、図解と実践例を交えて解説。
- 経絡に基づく施術の流れや、症例に応じた適切なアプローチ法を、実際の施術現場での応用に向けて徹底的に磨き上げます。
第4章:精・気・神
- 生命の三要素の統合的理解
精、氣、神は、身体の健康と病態の根源を成す重要な要素です。
第5章:津液
- 身体を潤す津液の役割
津液は、栄養と潤いを供給する重要な要素です。- 生成・分布・代謝のメカニズムを理解し、津液不足や過剰がどのように病態に影響するか、実例を通じて学びます。
第6章:氣血栄衛論
- 氣・血・栄・衛の総合的アプローチ
この章では、氣と血の循環、栄養の供給、そして防衛機能のバランスを体系的に学びます。- 経栄と栄養の違い、そしてそれぞれがどのように連携して健康を維持するかを、最新の臨床知見と古典理論を融合させて解説します。
第7章:病因論
- 病因とその多面的解析
病気の原因は、外因・内因、さらには情志や飲食・労倦といった生活習慣にまで及びます。- 六淫や七情の影響、飲食や五味、房労による影響を具体的な症例とともに検討し、病因解明のプロセスを学びます。
第8章:法則の部
- 八綱理論と症候分類法の実践
治療における基本的な判断軸となる八綱理論や、症状を体系的に分類する症候分類を学びます。
第9章:四診法
- 四診(望・聞・問・切)の徹底活用
古典的診断技術である四診法を、現代の臨床に応用するための詳細な手法と技術を伝授します。- 各診法の具体的な実践例や、微妙な触診のコツなど、徹底した実技指導を通じて、診断力を向上させます。
第10章:治法
- 多角的な治療アプローチの習得
養生法、経絡治療の応用、病理に基づく治療法、補瀉のテクニック、正治・反治や標治・本治の考え方など、多面的な治療法を実践的に学びます。
実技指導と使用器具

井上式八分長柄鍼の特長
経絡治療の核心技術として
この鍼を用いて治療することで、経絡上の微細な触覚所見や皮膚のツヤ、肌肉の弾力、栄養状態などが瞬時に把握でき、治療効果の確認が容易になります。
革新的なデザインで微細な操作を可能に
井上恵理先生が考案されたこの鍼は、鍼柄と鍼体が同一長で設計されており、従来の鍼では実現できなかった微妙な鍼の操作が可能になります。
鍼汪会の実技指導

3人一組のグループ指導、リアルタイムでのフィードバック
ベテランの先生が直接指導にあたり、各参加者の技術向上を丁寧にサポートします。
施術中の細部にわたる触診や動作の確認を行い、その場で改善点を具体的にフィードバックすることで、技術を磨くことができます。
研究会でのディスカッションと発表

古典と臨床の融合
研究会では、素問、霊枢、難経などの古典文献に基づく知識と、現場での臨床経験を統合し、理論と実践の双方から議論を深めます。
講演テープとディスカッション
故井上恵理先生や故二階堂宜教先生の講演テープを教材とし、二人一組のチームで発表を行い、会員同士で活発な討論を実施。
最新の知見と伝統の融合
このプロセスにより、単なる知識の暗記にとどまらず、実際の症例に基づいた柔軟な対応力が養われ、伝統医学の深い理解と応用力が飛躍的に向上します。
最後に
北海道漢方鍼汪会の経絡治療勉強会は、古典医学の真髄を学び、現代の臨床に即した実践技術を習得するための勉強会です。
参加者は、基礎理論から実践技術まで、徹底的に研鑽を積むことで、患者さんの根本的な治療に直結する高い技術力と判断力を身につけることができます。
古典と現代、理論と実技が融合したこの学びの場で、あなたも真の鍼灸師としての成長を実感してください。