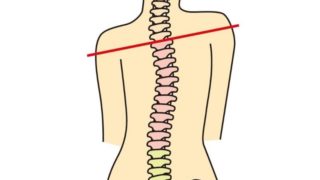鍼灸(しんきゅう)は、東洋医学の理論に基づき「身体が本来持っている力」を最大限に引き出す施術です。よく「鍼灸を受けてすぐ良くなった」という人がいる一方、「あまり変化を実感できなかった」という方もいます。この差を生む決定的な要因は、「自然治癒力(免疫力や回復力)の差」だと考えられます。
自然治癒力とは何か?
- 身体が自分自身を修復する能力
転んで擦りむいた傷が自然にふさがるように、人間の身体は本来、自らを回復させる仕組みを持っています。鍼灸では、この仕組みを刺激してより有効に働かせることが目的です。 - 病気や体調不良を根本から立て直す力
頭痛や肩こりなどの表面的な症状を一時的に抑えるのではなく、原因を内側から改善していくのが自然治癒力の本質です。
鍼灸が行う「身体の反応の調整」
東洋医学において鍼灸は、ツボ(経穴)や経絡(けいらく)を活用して、身体が本来持っている回復のスイッチを押します。これは次のようなイメージで捉えるとわかりやすいでしょう。
- スイッチを押す役割:鍼灸師
- 患者さんの症状や体質を見極め、的確にツボを刺激することで身体の反応を変えたり、高めたりする。
- 本質的に治すのは患者さん自身の力:自然治癒力
- 鍼灸師がどれだけ丁寧に施術しても、身体自体の回復力が乏しければ「引き出す材料」が足りません。
たとえば、怪我をしたときに病院で処方された薬や処置が「回復をサポート」してくれるのに対し、傷を塞いでいるのはあくまでも患者さん自身の身体です。鍼灸も同様に「身体を本来の整った状態に近づけ、治る力を働かせる」サポート役といえます。
「治る人」「治りにくい人」の違い
自然治癒力の“貯金”の有無
鍼灸では身体の調節を行い、回復反応を“引き出す”ことを目指します。しかし、引き出しを開けても中身(自然治癒力)が空っぽであれば、引き出せるものはありません。すぐに改善を感じられる方は、自然治癒力の“貯金”がしっかりある場合が多いのです。
逆に、自然治癒力が不足していると?
- 初回から劇的な変化を実感しにくい
- 改善までに時間や回数を要する
- 適切な食事・呼吸など、生活習慣の見直しも同時に必要になる
ここで大切なのは、「自然治癒力が足りなければ育てればよい」という考え方です。鍼灸師は、身体を整備して回復しやすい状態を作りながら、自然治癒力を高めるお手伝いもできます。
「治る人」「治りにくい人」の違い
自然治癒力の“貯金”の有無
鍼灸では身体の調節を行い、回復反応を“引き出す”ことを目指します。しかし、引き出しを開けても中身(自然治癒力)が空っぽであれば、引き出せるものはありません。すぐに改善を感じられる方は、自然治癒力の“貯金”がしっかりある場合が多いのです。
逆に、自然治癒力が不足していると?
- 初回から劇的な変化を実感しにくい
- 改善までに時間や回数を要する
- 適切な食事・呼吸など、生活習慣の見直しも同時に必要になる
ここで大切なのは、「自然治癒力が足りなければ育てればよい」という考え方です。鍼灸師は、身体を整備して回復しやすい状態を作りながら、自然治癒力を高めるお手伝いもできます。
自然治癒力を育てるお手伝いの具体例
- 胃腸機能の調節で消化吸収を助ける
- 胃や腸の働きが弱まると、せっかく栄養のある食事を摂っても十分に吸収できません。鍼灸による内臓機能の調整は、胃腸の動きを活性化し、栄養をしっかり取り込めるようサポートします。その結果、エネルギーや免疫細胞の生成を促進し、自然治癒力の“貯金”を少しずつ増やすことが期待できます。
- 呼吸を深くしやすい身体づくり
- 鍼灸では、肩まわり・背中・胸郭(きょうかく)などの筋肉の緊張を緩め、呼吸が浅くなる原因を和らげるアプローチも重要です。呼吸が深くなれば酸素の取り込みが効率的になり、細胞に新鮮な酸素が行き渡って身体全体の活力が高まります。とくにストレス過多で呼吸が乱れやすい方にとっては、鍼灸による呼吸機能のサポートが大きな手助けとなるでしょう。
こうした方法を組み合わせながら、自然治癒力の少ない方でも時間をかけて体質改善をはかることができます。施術を積み重ねる中で、少しずつ身体が変わっていく感覚を得られるはずです。
車の整備士に例える鍼灸の役割
鍼灸師を「車の整備士」にたとえると分かりやすいでしょう。エンジンやサビついたパーツをメンテナンスして、車が動く土台を整えるのが鍼灸師の仕事です。しかし、いくら整備が完璧でも、ガソリン(エネルギー源)が入っていなければ車は動きません。ここでいう「ガソリン」に当たるのが、栄養(食事)と呼吸から得られるエネルギーです。
- 鍼灸師の役割
- エンジン(身体)の不調部位をメンテナンスし、回復しやすい状態を整える
- 胃腸機能や呼吸機能など、自然治癒力の源となる部分を刺激・調整する
- 患者さん自身が担う部分
- 良質な食事・休息・呼吸法など、継続的なセルフケア
- ストレスをうまくコントロールする意識づけ
自然治癒力を高める二大要素
鍼灸が身体を整えることに加え、以下の2つの要素を見直すことで自然治癒力は大きく底上げされます。
1. 食事(栄養)
- 身体の材料を補う
筋肉や血液、ホルモンや免疫物質など、健康を維持するために必要なものは基本的に食事から作られます。鍼灸で胃腸機能をサポートすることで、この「材料づくり」の効率がさらに高まるでしょう。 - 東洋医学的な食の考え方
「身体を温める食材」「冷やす食材」など、食べ物にはさまざまな性質があります。個々の体質に合わせて食事内容を少しずつ見直すことが、自然治癒力アップにつながります。
2. 呼吸
- 酸素の交換が身体をリフレッシュさせる
深くゆっくりした呼吸は、血液中の酸素と二酸化炭素の交換をスムーズに行い、細胞に新鮮な酸素を届けます。鍼灸で呼吸を妨げる筋緊張を緩和すれば、自然と呼吸が深まっていきます。 - ストレスによる呼吸の浅さ
ストレスや緊張が強いと、無意識に上半身に力が入り、胸や肩まわりが硬くなって呼吸が浅くなります。浅い呼吸が続くと細胞に十分な酸素が行き渡りにくくなり、回復力や体力の低下を招きやすいです。
鍼灸施術は「身体を整える」ものであって、「直接治す」ものではない
鍼灸は症状そのものを“外部から取り除く”のではなく、「身体が自ら治せる状態」に再調整します。痛みや不快感が生じる部位だけでなく、生活背景や体調全体を総合的にみることが必要です。
- 鍼灸師にできること
- ツボや経絡を通じて“回復スイッチ”を押し、反応を起こしやすくする
- 不足している力(自然治癒力)を補うため、食事・呼吸・睡眠などの改善をアドバイス
- 心身の緊張を緩和し、めぐりを整える
- 患者さん自身にしかできないこと
- 栄養補給や呼吸法、日々のセルフケアを継続する
- ストレスマネジメント(呼吸法の意識、休息の確保など)
- 十分な睡眠や休養を確保し、生活リズムを整える
このように、鍼灸施術と患者さんご自身の努力が両輪となって自然治癒力を育んでいきます。
すぐ治る人・時間がかかる人、それぞれの特徴
すぐ治る人
- 体力・免疫力が充実している
- 食生活や睡眠習慣が良好で、栄養不足や慢性疲労が少ない
- ストレスケアがうまくできており、呼吸が浅くなることが少ない
時間がかかる人
- 慢性的な疲労や強いストレスなどで自然治癒力が低下
- 食事バランスが乱れている、あるいは呼吸が常に浅い
- エネルギーの“貯金”を蓄えるところから始める必要がある
時間がかかるケースでも、適切な施術と生活習慣の見直しを続けることで、少しずつ改善の兆しが見えてくることが多いです。
まとめ:自然治癒力を高め、鍼灸を味方につける
- 鍼灸は身体をリセットし、治癒力を“引き出す”ための手段
- 自然治癒力は誰しもが持っているが、その量には個人差がある
- 食事や呼吸に着目し、ストレスを上手にケアすることで大きく底上げできる
- 身体が整うスピードは人によって異なるため、焦らず続けることが大切
すぐに改善を感じる方もいれば、時間を要する方もいます。その違いは「身体がため込んできた自然治癒力の余力」によるものです。しかし、自然治癒力が乏しくても、鍼灸施術とセルフケアを組み合わせることで高めることは十分に可能です。胃腸機能や呼吸機能を整えながら、日々の食事やライフスタイルを見直していけば、身体は少しずつ本来の力を取り戻していくでしょう。
執筆者
徳田 和則
鍼灸師・柔道整復師/北海道漢方鍼汪会会長/奈良県出身・北海道大学卒。2008年に「徳田漢方はり院」を開業。東洋医学をベースとしたアプローチで、患者さん自身の持つ自然治癒力を最大限に引き出す施術を行っている。専門家としての視点から、一人ひとりの体質・症状に合わせたアドバイスやサポートを提供中。
「身体の声を聴き、自分の健康を守る力を養う」ことを大切にしながら、鍼灸による根本的なケアを広めている。体調を整える第一歩として、ぜひ鍼灸を取り入れてみてはいかがでしょう。