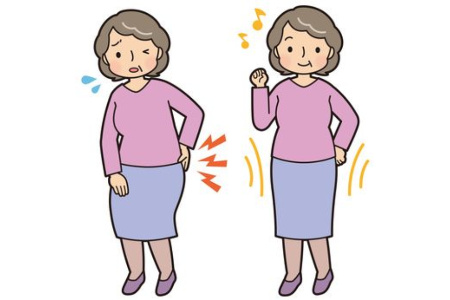【ヘルニアとは?――基礎知識】
ヘルニア(椎間板ヘルニア)とは、背骨(脊椎)を構成する椎骨の間にある「椎間板」の内側にある髄核というゼリー状の組織が、何らかの要因で外へ飛び出してしまい、神経を圧迫する状態を指します。専門的には以下のように分類されます。
- 脱出:椎間板の外周を取り巻く「線維輪(せんいりん)」が切れて、中の髄核が飛び出している状態
- 突出:線維輪に亀裂が入っているものの、完全には断裂しておらず、髄核が突き出して神経を圧迫している状態
いずれも神経を刺激するため、強い痛みやしびれを引き起こすことがあります。とくに腰椎に生じる場合(腰椎椎間板ヘルニア)が多く、一般的には「腰のヘルニア」と呼ばれます。首に生じた場合(頚椎椎間板ヘルニア)は、腕や手先のしびれ・痛みが目立つことが多いです。
【ヘルニアの主な症状】
- 腰痛・首痛:後ろに反らす(後屈)動作で特に痛みが増すことが多い
- しびれや痛み:腰から足先にかけて(坐骨神経痛)、または首から腕にかけて神経症状が広がる
- 感覚障害・冷感:神経が強く圧迫されると、触覚や痛覚が鈍くなったり冷感が生じる
- 筋力低下:足や指先に力が入りにくい、うまく動かない
- 排尿障害:重度の場合、膀胱や直腸の神経が影響を受け、尿が出にくい・コントロールしづらいなどの症状が出ることもある
症状の程度は人によってさまざまです。医師から「手術しても100%痛みが消えるわけではない」と説明を受けるケースもあり、治療方針の選択には時間をかけて検討が必要です。
【西洋医学的な治療――保存療法と手術】
1. 保存療法
まずは数ヶ月ほど手術以外の「保存的」な治療が行われることがほとんどです。
- 消炎鎮痛剤(湿布・内服薬):痛みを和らげ炎症を抑える
- 注射:トリガーポイント注射や硬膜外ブロック、神経根ブロックなど、痛みや炎症のある部位を集中的に鎮める
- 牽引療法:腰や首を引っ張ることで椎間板や神経への圧迫を軽減する
- 温熱療法:血行を良くして筋肉の緊張をやわらげる
- 体操療法:理学療法士などの指導のもと、腰背筋や腹筋を鍛えて負担を減らす
- コルセットの使用:患部を安定させる
2. 手術療法
保存療法で効果が得られず、「痛みが非常に強い」「仕事や日常生活に大きな支障が出る」「神経症状が進行している」などの場合、手術が選択されます。飛び出した椎間板を取り除いたり、神経への圧迫を軽減することを目的とします。しかし、手術をしても痛みやしびれが完全に消失しないケースもあるので、十分なカウンセリングや経過観察が大切です。
【東洋医学的なアプローチ――原因を多角的にとらえる】
東洋医学(漢方や鍼灸)では、ヘルニアの症状を「経絡(けいらく)」や「気血水(きけつすい)」、さらには「五臓六腑(ごぞうろっぷ)」の働きの乱れとして捉えます。初心者の方に向け、用語を簡単に解説すると下記の通りです。
- 経絡:ツボ同士を結ぶ道筋のことで、体内を巡る“気や血”などの通り道。道路のようなイメージで、流れが悪いと痛みやコリが生じる
- 気血水:「気」(エネルギー)、「血」(血液)、「水」(体内の水分やリンパなど)を総称し、東洋医学ではこれらの偏りや不足が病気の原因になると考える
- 五臓六腑:肝・心・脾・肺・腎などの内臓機能を広く捉えた概念。西洋医学でいう実際の臓器だけでなく、体全体の機能やエネルギーの連動を指す
経絡のバランスを整える
ヘルニアは神経圧迫だけでなく、筋肉・腱の緊張も大きく影響します。とくに「後ろに反らすと腰が痛い」「股関節までつっぱる」などの場合、東洋医学では肝経(肝の経絡)の問題としてみることが多いです。曲げ伸ばし両方で痛みがあるなら肝経と腎経(腎の経絡)の双方を調整するケースもあります。
鍼灸治療では、痛みが出ている部位だけでなく、全身の経絡を丁寧にみて流れを調整し、筋肉や腱が自然にゆるむよう導いていきます。
五臓六腑をケアして筋肉と腱を養う
東洋医学では、筋肉や腱を養う働きは肝や脾(ひ)と深く関係していると考えます。肝や脾の機能が整えば、筋肉や腱がやわらかく保たれ、結果的に腰痛やヘルニア症状が軽くなるとされます。鍼灸はもちろん、食事や生活習慣の見直しを含めたアドバイスが行われることも多いです。
気血水の乱れを整える
「動かすと痛い」「押すと痛む」タイプの腰痛は、外部からの刺激(東洋医学でいう“邪気”)が原因の場合が多いと考えます。一方、「押すと不快感がある」「重だるい」「じっとしていても痛い」場合は、身体の内側のエネルギー不足(生気の損傷)が原因かもしれません。その場合は、自然治癒力を引き出すため、睡眠や食事の質も含めた生活全般の見直しが重要になります。
【治療を受ける方へ――不安をやわらげるポイント】
- 問診・検査でしっかり原因を把握する
ヘルニアの症状は個人差が大きいので、医療機関でMRIなどの検査を受け、原因を特定することが大切です。症状によっては手術が適切な場合もありますが、先に保存療法や東洋医学的ケアを試すことで改善するケースも多々あります。 - 複数の選択肢を知る
西洋医学(整形外科・リハビリ)と東洋医学(鍼灸・漢方)を組み合わせると、より効果的に痛みやしびれを改善できる可能性があります。「どちらが正しい」ということではなく、自分に合った治療法を探す姿勢が大切です。 - セルフケアの習慣を身につける
- 痛みが少し落ち着いてきたら、医師や鍼灸師、理学療法士から指導を受けて、軽いストレッチや体操を継続する
- 生活リズムを整え、適度な睡眠とバランスの取れた食事を心がける
- ストレスや疲れをため込みすぎないよう、休養をしっかりとる
「ヘルニア」という言葉の印象から強い不安を感じる方は少なくありません。しかし、腰や首に負担のかかる動作を見直し、医療の専門家の指導を受けながら適切な治療とセルフケアを行うことで、多くの方が痛みやしびれの軽減を実感しています。場合によっては、東洋医学のアプローチを加えることで筋肉と経絡のバランスを整え、自然治癒力を引き出すことも十分期待できます。
【まとめ――多角的な視点でヘルニアをとらえよう】
- ヘルニアは20~40代に多いが、若年層から高齢者まで幅広く発症する
- 後屈(腰を反らす動作)で痛みが強まったり、神経圧迫によるしびれや感覚障害が起こる
- 保存療法(薬物、注射、温熱、牽引など)と手術療法の両方がある
- 東洋医学では「経絡」「気血水」「五臓六腑」の乱れを整えることで筋肉や腱を柔軟にし、痛みやしびれを軽減させる
- 生活習慣やセルフケア(運動・休養・食事など)も大切であり、症状に応じた対策を続けると改善する例が少なくない
ヘルニアに限らず、腰痛全般に悩む方は「どの治療が自分に最適なのか」「手術をする必要があるのか」と不安を抱えることが多いでしょう。専門家に相談しつつ、自分に合った方法を見つけることが、症状緩和への近道です。また、鍼灸のように身体を総合的に調整する療法も選択肢に加えれば、痛みの根本改善に向けたサポートとなる可能性があります。